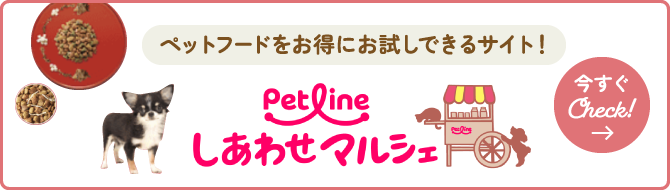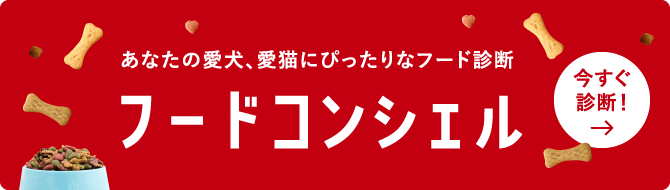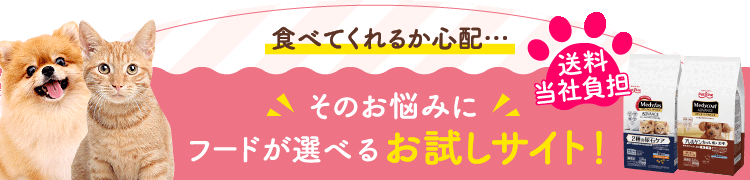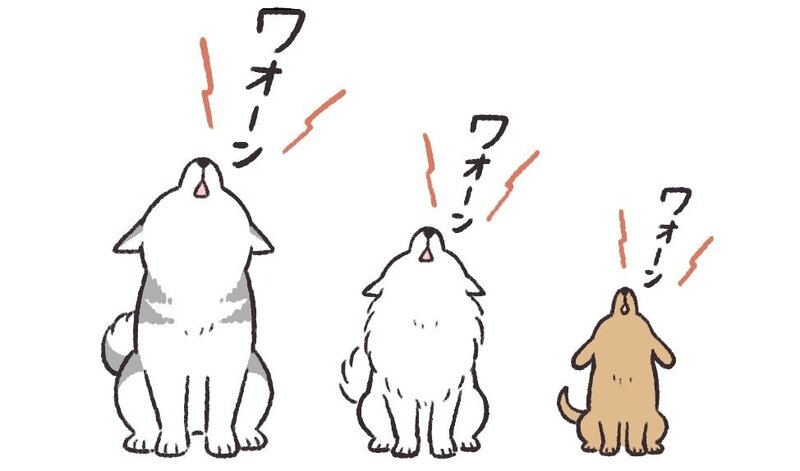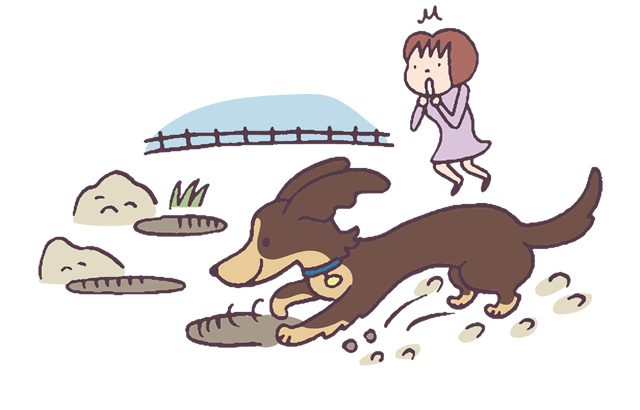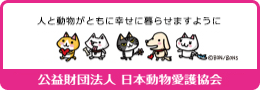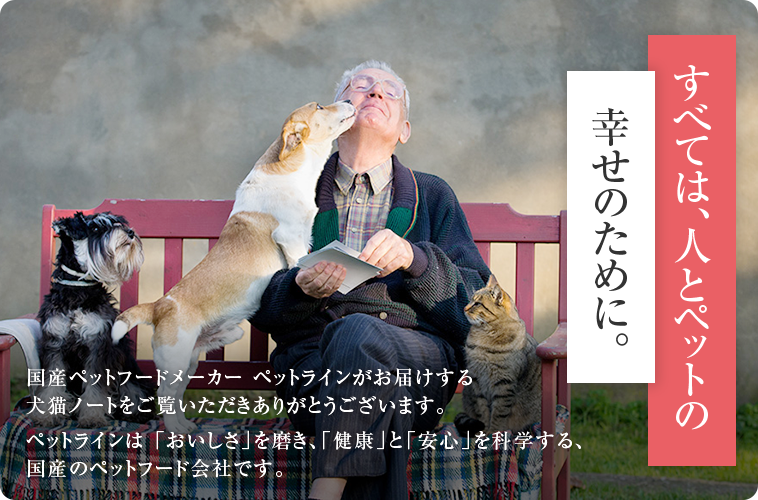メスの犬はオスより飼いやすい?家族に迎える前に知っておきたいこと
- 公開日:
犬を家族に迎える時に、犬の性別を考慮することは大切です。メス(雌)とオス(雄)では異なる特性があり、オスの犬よりもメスの犬の方が飼いやすいと感じる人もいれば、その逆の意見もあります。この記事では、メスのわんちゃんを家族に迎えるにあたって事前に考えておきたいポイントをご紹介します。犬を家族に迎えたいと思っている人は、ぜひ参考にしてください
この記事の監修者


メスの犬の特徴
「犬はメスの方が飼いやすい」と耳にすることがあるかもしれません。確かに、メスの犬はオスの犬とは異なる特徴があります。以下では、メスの犬の特徴について詳しくご紹介します。
メスの犬の体格や性格
同一犬種において、メスの犬はオスの犬に比べて体格が小柄な傾向にあります。メスの犬の性格は、一般的にマイペースで穏やかな性格と言われています。オスの犬と比べて落ち着きがあり、しつけをしやすい傾向にあります。初めて犬を家族に迎える人や、愛犬とのんびり過ごしたいという人に向いているでしょう。
トイレ
犬のトイレは片足をあげて行うイメージがありますが、メスの犬はオスの犬とは異なり、通常しゃがんだ姿勢で行います。まれにオスの犬のように足をあげてトイレをするメスの犬もいますが、それはマーキングと関係しているという報告もあります。
マーキング
マーキングとは、自分の縄張りを示すために、少量の尿をあちこちにかける行動のことです。通常はオスの犬が行う行動ですが、避妊手術を受けていないメスの犬も発情期に自分の存在をオスに知らせるためにマーキング行為をすることがあります。
ヒート
ヒートとは、発情期に見られる生理のことです。メスの犬のヒートは犬の生殖活動にとって重要です。ヒートは生後約5カ月から13カ月で始まりますが、小型犬の方が早い傾向にあります。その後約6カ月から10カ月ごとに訪れ、外陰部の腫れや出血が見られます。出血が少量の場合、犬がなめてしまうので飼い主さんは気づかないこともあります。ヒート中には、よく吠えたり人や物に体をこすりつけたりする行動が見られます。人間のような生理痛はほとんどないと考えられています。
メスの犬がかかりやすい病気
メスの犬がかかりやすい病気はいくつか存在しますが、ここでは4つの病気をご紹介します。
子宮蓄膿症
子宮蓄膿症とは、子宮が細菌感染を起こして子宮内部に膿が溜まる病気です。子宮蓄膿症になると次のような症状が見られます。
- 飲水量が増えて尿量が増える
- 外陰部を気にしてなめる
- 外陰部から膿が出ている
- 発情期の出血が健康な状態の時に比べて長期間である
- 元気がない、食欲不振
- 嘔吐をする など
子宮蓄膿症は早く治療をしないと死に至る病気です。そのため、メスの犬が子宮蓄膿症を発症した場合は、子宮の摘出手術を行います。子宮蓄膿症は避妊手術によって予防できる病気です。
乳腺炎
犬は左右に5組ずつ、合わせて10個の乳頭がついていて、母乳を出すための乳腺があります。この乳腺が何かしらの原因で炎症を起こしている状態を乳腺炎と言います。また、乳腺炎は避妊をしていないメスの犬に多く見られる傾向にあります。乳腺炎になると次のような症状が見られます。
<軽度>
- 乳頭が熱っぽい、痛みがある
- 出産をしていないのに乳房が張る、黄色っぽい乳汁が出る
<中度>
- 元気がなくなり食欲不審になる
<重度>
- 乳房にしこりができる
- 茶色っぽい乳汁に血が混じる
細菌感染を伴う場合には、皮膚が壊死や壊疽(えそ)することがありますので、重症化する前に動物病院に連れて行き、適切な治療をしてもらいましょう。
乳腺腫瘍
乳腺腫瘍は10歳以上のメスの犬に多く見られる腫瘍です。避妊をしていないメスの犬に多い傾向にあります。乳腺の組織の一部が腫瘍化してしこりができ、しこりが小さいうちは良性のものがほとんどで、多くが手術で根治が可能ですが、大きくなると悪性になるものも出てきます。原因は、乳腺の細胞が女性ホルモンの影響を受け増殖することで腫瘍になります。そのため、若いうちに避妊手術をすることで発生率を下げることができます。悪性腫瘍の場合や治療が遅れた場合には、周囲のリンパ節や肺などに転移し、それらが腫瘍に侵されることによって、死に至ることもあります。
乳腺腫瘍は、しこりができる前に発見することは難しく、しこりが大きくなる前に見つけることが早期発見の鍵となります。日頃から愛犬を抱っこする際や撫でる際に乳腺周りを意識的に触れ、いつもと違う腫れやしこりを感じたら、すぐに動物病院で診察を受けることをおすすめします。
膀胱炎
メスの犬がかかりやすい病気のひとつに膀胱炎があります。メスの犬はオスの犬より尿道と肛門の位置が近いため、細菌感染しやすい傾向にあります。また膀胱炎は慢性化する恐れがある病気です。膀胱炎になると次のような症状が見られます。
- トイレの回数が増える
- 排尿時に痛みを感じて、排尿を嫌がったり、排尿に時間がかかったりする
- 症状が悪化すると尿がにごり、ピンク色の血尿が出る
メスの犬の体調管理
犬は人間より何倍ものスピードで成長するため、日頃から体調の変化に気を付けることが重要です。ここでは、メスの犬を家族に迎える際に気を付けておきたい体調管理についてご紹介します。
食事について
肥満にならないように体重管理をする必要があります。適度な散歩や遊びで運動を して 、食事の与え方にも気を付けましょう。メスの犬の食事はオスの犬と同じように、年齢に合った食事を与えることが大切です。例えば、成長期の子犬であれば栄養価の高い子犬専用フードを与えます。そして、成犬になったら成犬専用フードを選び、シニア期を迎えたならばシニア犬専用フードを与えましょう。
メスの犬はオスの犬より筋肉量が少なく、1日に必要なエネルギー量も少ないため、 オスの犬と同じ食事量だと肥満になる可能性があります。
避妊手術について
メスの犬は避妊手術をすることで発情期の出血を避けることができ、様々な病気の予防にも役立ちます。これからメスのわんちゃんを家族に迎えることを考えている場合、避妊手術の検討をおすすめします。動物病院では、早期の避妊手術を勧められることが多いでしょう。避妊手術には以下のメリットがあります。
- 特定の病気を予防できる
- 性ホルモンに関連した問題行動を抑制できる
- 望まない妊娠を防止できる
また、避妊手術をすると肥満のリスクが高まるため、食事の与え方や日頃の体調管理に注意が必要です。
まとめ
メスのわんちゃんを家族に迎える際に考慮したいポイントを紹介しました。オスの犬とメスの犬ではそれぞれ異なる特徴があるため、メスの犬はメスの犬に適した環境を整えてあげることが大切です。
この記事がメスのわんちゃんを迎えたいと思っている人の参考になれば幸いです。